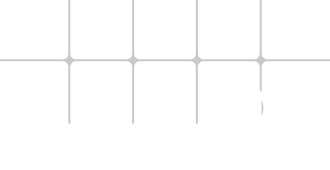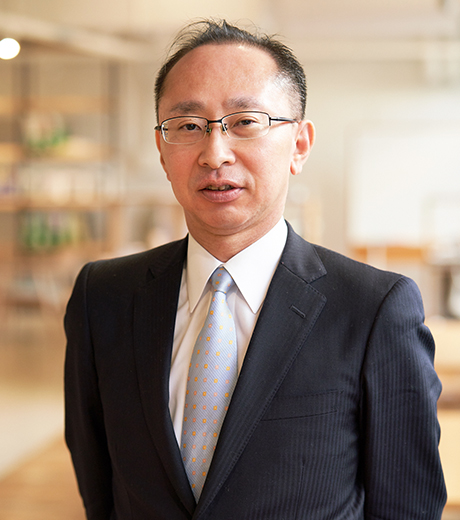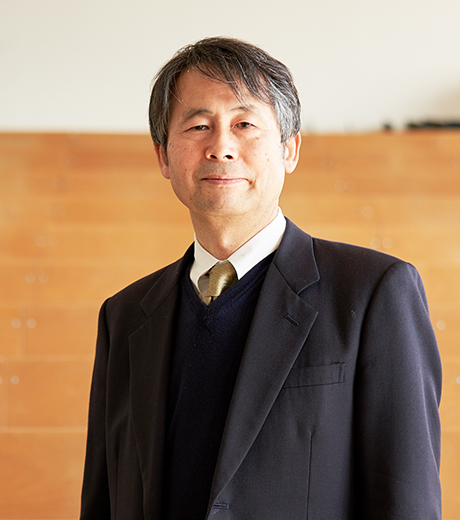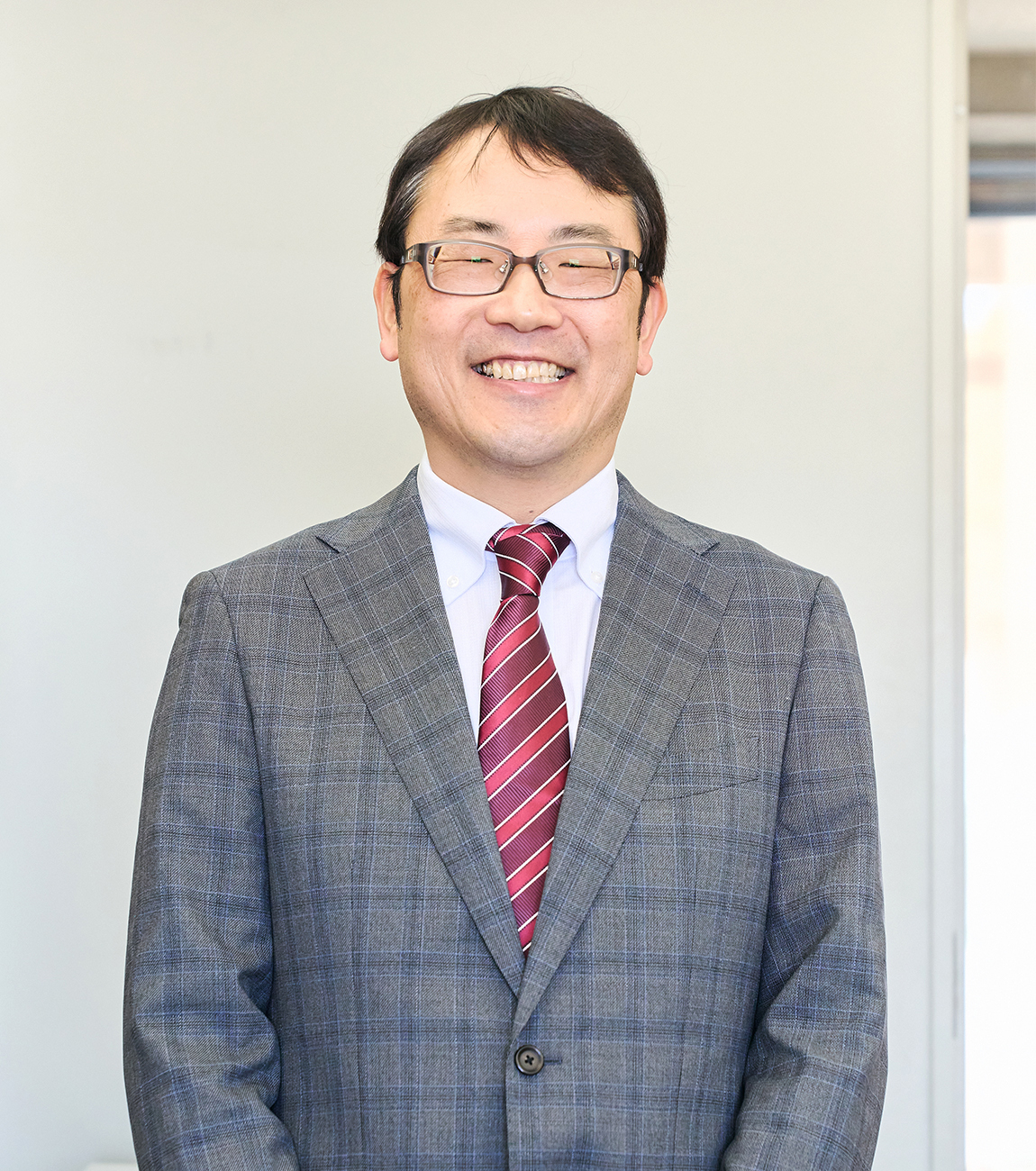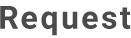Takatsugu Watanabe
渡邉 孝継准教授
- プロフィール
聖学院大学心理福祉学部准教授。立教大学大学院現代心理学研究科博士前期課程修了(修士・心理学)、立教大学大学院現代心理学研究科博士後期課程単位取得満期退学。埼玉県本庄市発達教育支援センター すきっぷ 心理職。趣味はキャンプと、チーズの燻製。
-
専門分野
応用行動分析学、障害者・障害児心理学
-
研究テーマ
自閉スペクトラム症児へのコミュニケーション支援
-
講演可能なテーマ・ジャンル
- 発達障害児の理解と支援
- 通常学級で発達障害のある子どもたちへの具体的な対応を考える
- イヤイヤ期の子どもとの関わり方
- 小学校で成長するための大切なポイント
- 子どものアンガーマネジメント
先生の専門分野は、どのような学問ですか。
応用行動分析学とは、人の行動を科学的に分析し、環境を調整することで望ましくない行動を減らし、望ましい行動を増やすための心理学的手法を学ぶ学問です。行動に焦点を当てるため、自分の考えを言葉で説明できない小さな子どもにも応用できます。
例えば、スーパーマーケットで床にひっくり返って「お菓子買って」と泣いている子がいるとしますね。私たちは行動の「前後」に着目します。まず、行動の「前」に着目し、何がその行動のきっかけになったのかを分析します。今日きっかけになったのは、お菓子が目に入ったことです。お菓子やおもちゃなど子どもの好みのものを売っていない店に行った時は、その行動は起こらないでしょう。次に着目するのが行動の「後」です。この子がこの行動によって得ているものは何でしょうか。例えば、お父さんからの「今日はお菓子は買わないんだよ」という言葉ですね。やさしい声色を聞き、その子は「もう少し粘れば買ってもらえるかも」と感じるかもしれません。それで、いっそう手足をバタつかせて騒ぐのです。でも、もしお父さんがその行動にほとんど反応せず、カートを押して別の売場へ進んでいったらどうでしょう。その子は続けてもムダであることを察し、泣き止んでしぶしぶ後ろをついていくはずです。子どもが追いついてきた時に「偉いね」と褒めることで、「お菓子を買わないときには、お父さんの後ろについていく」行動が増えます。お菓子が並んでいる棚を避けたり、泣き始めた後の対応を工夫することで、子どもの望ましくない行動を減らし、望ましい行動を増やすことは可能です。泣いている子に丁寧に寄り添うことも大切ですが、子どもに「大人の注意をひく」「お菓子を得る」などのねらいがある場合は、対応を工夫しないと望ましくない行動がヒートアップする場合もあります。そんな時に役立つのが、応用行動分析学の学びなのです。
取り組んでいる研究について詳しく教えてください。
応用行動分析学は子どもから大人まであらゆる人に用いられる手法ですが、特に発達障害児への支援で用いられています。私の研究テーマは「自閉スペクトラム症(Autism Spectrum Disorder;ASD)のお子さんへのコミュニケーション支援」です。ASDのお子さんと保護者の方に協力いただき、大学で学生と一緒に個別支援プログラムを行っています。ASDのお子さんは、相手の気持ちを想像することが苦手で、「太っているね」などと思ったことをそのまま口に出してしまうことがあります。「失礼な子」と思われがちですが、本人は「なんでうまくいかないんだろう」と対人関係にストレスを抱えています。私が研究しているのは、対人関係で生じるストレスを緩和する方法です。2024年に科学研究費の助成を受けて調査したのは「ASDの子どもと10分間、子どもの好きなものについて会話をする」ということが、子どものストレス値を下げるかどうかの検証です。「会話するだけ?」と思うかもしれませんが、人は他者と楽しく会話をするだけで、ストレスが緩和します。ASDのお子さんも同様です。保育・教育現場の先生方にしてみれば、子どもが好きな「キャラクター」や「ゲーム」を切り口にした声かけなど、毎日当たり前にやっていることです。これらの“手法”に効果があることを示すことができれば、より多くの場面で先生方にこの手法を活用してもらえると考えます。家庭でも同様です。学校でうまくいかなかった子が、家に帰って家族と大好きな「恐竜」の話をしたことで、気持ちがすっきりするかもしれない。そうした希望を持ちながら論文を書いているところです。ASDのお子さんの特性は本当にさまざま。ユニークな愛らしさを持つ子どもたちに会えるのが研究の楽しみです。一人ひとりのその子らしさを伸ばしつつ、みんなが楽しく過ごせるヒントを、これからも研究を通して見つけていきたいと思います。
著 書
-
標準公認心理師養成テキスト
共著 編集者:大石幸二・池田健・太田研・大林裕司 共著者:朝倉新・池田健・大石幸二・太田研・大橋智・大林裕司・財津康司・下山真衣・玉澤知恵美・中内麻美・成瀬雄一・羽澄恵・平野貴大・米山直樹・渡邉孝継・坂本真季・竹森亜美・和田恵
担当頁:pp.24-39,168-175,176-177,202-207 文光堂 (2022年6月)公認心理師試験で問われる内容が厳選されている。テーマごとに図表や重要語句の欄外説明を含んだ見開き構成となっており、標準的な情報・知識が整理されている。第1章と第5章を担当。
-
特別支援学校 教育実習ガイドブック ―インクルーシブ教育時代の教員養成を目指して―
共著 遠藤愛(編著) 共著者:宇田川和久・太田研・須藤邦彦・髙橋幸子・栃金聡・山口伸一郎・渡邉孝継
担当頁:pp.47-50,53-54,58 学苑社 (2022年4月)特別支援学校教員をめざす学生にとって、教育実習は「教員」を経験する初期学習経験である。この初期学習経験は、今後の学生の特別支援教育への学習意欲や、「教員になる」という就業意欲を喚起する基軸となる。本書は、この教育実習をより効果的に行うための手引書である。養成校で実習生が教科書として用いることを想定し、学生目線で手引きする。同時に、学生が初任者として教員になる際にも活用できる内容となっている。第3章を担当。
-
学校コンサルテーション -統合モデルによる特別支援教育の推進-
共著 大石幸二(編著) 共著者:野口和也・須藤邦彦・遠藤愛・中内麻美・大橋智・太田研・渡邉孝継・須田なつ美・林勇輝
担当頁:pp.1-22,87-110,275-283 学苑社 (2008年11月)心理職や巡回相談員、地域支援を担当するコーディネーターが相談を受けるコンサルタントとして、教師に対する支援を効果的に実践するための情報と技術を記載した。特に経験の浅いコンサルタント、これからコンサルテーションの実践を考えている大学院生の一助となりえる情報が盛り込まれている。第1章と第4章、用語集を担当。
-
標準公認心理師試験対策問題集 2020
共著 大石幸二(編著) 共著者:池田健・大石幸二・太田研・大橋智・大林裕司・下山真衣・玉澤千恵美・中内麻美・成瀬雄一・羽澄恵・平野貴大・米山直樹・渡邉孝継
担当頁:pp.128-130,136-139,141-142,233,449,456,476 文光堂 (2020年4月)公認心理師試験を受ける方のための書籍である。公認心理師養成に関わる教員と臨床家(医師・心理職)による分担執筆が行われた一冊である。年々厳格化が予測される試験を乗り切るだけでなく、より深く病態を理解する真の心理専門職を目指す全ての受験者に推薦したい内容となっている。
-
先生のための保護者相談ハンドブック
-配慮を要する子どもの保護者とつながる3つの技術-共著 大石幸二(監修) 編著:竹森亜美・須田なつ美・染谷怜 共著者:中内麻美・脇貴典・渡邉孝継・近藤悠海
担当頁:pp.68-71,76-77 学苑社 (2020年2月)保護者と信頼関係をつくり、効果的な相談活動を展開するためのエッセンスが詰め込まれている。小中学校、特別支援学級、特別支援学校、通級指導教室などの担任教師に向けた書籍である。保護者相談の具体的な技術、事例、ワークシートから構成されている。特別支援教育や障害児教育、臨床心理学の視点が盛り込まれているが、平易な文章とイラストにより、初めて保護者相談に臨む教師や相談員も理解しやすい内容となっている。事例4、5、7を担当。
論 文
-
保育者養成校の大学生へのスタッフトレーニングの効果
-活動プログラムへの参加により習得される応用行動分析の知識の分析-渡邉孝継 人間関係学研究 28(1) 85-95 (2023年12月)
幼児と保護者との活動プログラムに参加している保育者養成校の大学生に対するトレーニングの効果について検証した。①活動プログラムへの反復参加と②活動の計画書作成・司会担当を行なった結果、①活動プログラムへの反復参加のみを行った大学生の応用行動分析に関する知識は上昇傾向を示したが、②活動の計画書作成支援を受けた大学生の知識は下降傾向を示すことを明らかにした。
-
Attention getting Behavior Acquisition from Others’ Speech in children
with Autism Spectrum Disorders.Takatsugu Watanabe. The Academic Canon of Arts, Humanities, and Sciences 3 153-168 (2020年3月)
1名の自閉スペクトラム症児が他者の聴覚的な注意方向を意識した伝達を可能になることを目的とした。指導開始前、対象児は他者の様子を窺うことなく、一方的に伝達を行なっていた。そこで、行動の見本を示すビデオ映像を用いて指導を行なった。その結果、指導終了後は他者が話している時は注意を喚起し、耳を澄ませている時には伝達を行うことが可能となった。以上から、自閉スペクトラム症児の他者の聴覚的な注意方向を意識した関わりの獲得可能性を示した。
-
自閉スペクトラム症児の対人葛藤場面における互恵的な分配行動の獲得
-他者との円滑な対人交渉を目指して-渡邉孝継・山口暁・豊田真季・竹森亜美・中内麻美・大石幸二 言語文化学会論集 50 139-151 (2018年8月)
自閉症スペクトラム障害児が、お菓子分配場面で、他者の好みと自身の好みの双方を勘案した分配行動を自発可能になるか検証した。介入で行動の見本を提示した結果、他者の好みと自身の好みの双方を勘案した分配行動を自発可能になった。このことから、自閉症スペクトラム障害児が対人葛藤場面において互恵的な分配行動を自発可能であることが明らかになった。以上から、自閉症スペクトラム障害児の他者とのコミュニケーションの円滑化が示唆された。
-
Relationship between Spontaneous Speech Function and Behavior Rating
Inventory of Executive Function Profile in Children with Autism Spectrum
Disorders:A Pilot Case Study.Kouji Oishi, Kunihiko Suto, Asami Nakauchi, Takatsugu Watanabe, Ami Takemori, Maki Toyota.
Psychology 8 2138-2145 (2017年11月)3人の自閉症スペクトラム障害児の自発的発話が行動の反応抑制と注意の切り替えと関連しているかについてBRIEF(実行機能に関する行動の評価尺度)を用いて調査した。その結果、自発発話の頻度が最も高い参加者は、切り替えが最も良く、最も活動的でない発語を有する参加者は切り替えが最も困難であった。以上の結果から、自閉症スペクトラム障害児の自発的な発話と切り替えの困難さは関連性があることと、今後の実行機能への支援の重要性を指摘した。
-
自閉性障害児における視覚的注意に関する応用行動分析的研究
-他者の視線方向の弁別と自己の応答の分化-渡邉孝継・須藤邦彦 教育心理学研究 59 100-110 (2011年4月)
自閉性障害児が、他者へ伝達を的確に行う場面では、他者が伝達物を見ているか否かを判断し、見ていない場合は、 他者の注意を引く行動を獲得した。対象児がどちらか一方のものを選択するという二者択一場面では、自身が有利になるような選択をするという行動を獲得した。以上のことから、自閉性障害児の注意を踏まえたコミュニケーション行動の獲得可能性を示した。
関連するSDGsのゴール
★学校法人聖学院はグローバル・コンパクトに署名・加入し、SDGsを目指した活動を行っています。